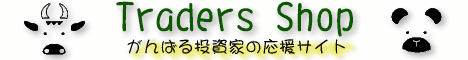
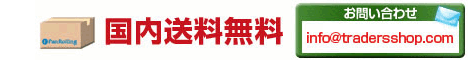
| 携帯版 |
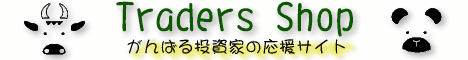
|
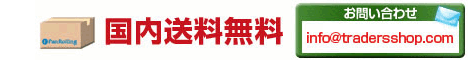
|
|
フィスコ投資ニュース配信日時: 2025/09/25 11:05, 提供元: フィスコ クオルテック Research Memo(5):自動車電動化と先端半導体が牽引する評価ニーズの拡大*11:05JST クオルテック Research Memo(5):自動車電動化と先端半導体が牽引する評価ニーズの拡大■クオルテック<9165>の今後の見通し 3. 事業環境 (1) 自動車業界の動向 大手自動車メーカー各社は電動化に向けた対応を加速させている。トヨタ自動車<7203>は、2030年にEV(電気自動車)販売台数350万台、本田技研工業<7267>は同年にEV販売台数200万台、日産自動車<7201>は2026年に電動車販売比率を44%以上とするなど、その動きは活発化している。2025年3月に経済産業省が公表した各社のEV関連投資額は、トヨタ自動車が2030年までに5兆円、本田技研工業が2030年度までに約10兆円(ソフトウェア含む)、日産自動車が2026年度までに2兆円となっており、EV開発・生産への積極姿勢がうかがえる。EV、HV(ハイブリッド自動車)、PHV(プラグイン・ハイブリッド自動車)、FCV(燃料電池自動車)など電動車において、パワー半導体や二次電池はキーデバイスとなる。特にパワー半導体は、PCU(パワーコントロールユニット)という、モーター制御や電力の変換・管理を制御する装置に使用されるため、電動車の性能向上にとって最も重要なデバイスとなる。このことからパワー半導体に関する信頼性評価は電動車の研究開発にとって必須といえる。 一方、二次電池はその性能が電動車の走行可能距離を左右する重要なデバイスとなる。現在は二次電池としてリチウムイオン電池が主流だが、軽量化や小型化、安全性の向上といった克服すべき課題が多く、解決に向け、自動車メーカーや電池メーカーは全固体電池の実用化を目指し研究開発を進めている。近い将来リチウム電池のみならず全固体電池に係る信頼性評価へのニーズも予想されるため、同社は全固体電池に関する信頼性評価を実施するための研究開発を進めている。 自動車の概念を変える技術革新「CASE」では、Connected通信、Autonomous自動化、Smart / Shared & Servicesシェアリング、Electric電動化の4領域で技術革新が進行中である。Connectedでは事故の自動通報や渋滞情報の共有の実用化が進んでおり、最近ではトヨタ自動車の「通れた道マップ」が災害発生時に道路の封鎖やう回路の情報を提供して実用化されている。Autonomousはレーザー光を使ったセンサー「Lidar」を活用し、自動運転レベル0-5のうち現在は、運転の主体がシステムとなるレベル3まで実用化されている。Smart / Shared & Servicesのカーシェアリングでは、車載システムからの情報を基に車両状態や課金の管理・制御を行っており、公共交通機関の充実と駐車場など保有コストの高さからクルマ離れの進む日本社会に浸透してきている。Electricについては、気候変動への対応から脱炭素社会実現に向け喫緊の課題として国家レベルで推進されている。同社は現在同領域で、ユーザーの安全を第一に安定したモビリティ技術を担保するため、試験・評価から解析までを一連して提供している。「CASE」での中心技術はソフトウェアとなるものの、それを駆動するために必須の半導体やハードは関連して性能が求められ、革新に伴い、同社評価事業へのニーズが高まることが予想される。部品単体からシステムを含む完成品まで総合的にカバーした試験に対応するTQSを提供するほか、これまでの実績では顧客の先行開発から量産開発、実用化まで受注するケースが多いこともあり、主要顧客の研究開発に伴走して試験・評価、故障解析の一連のサイクルを繰り返すことで、顧客のテクノロジー進展と相乗して同社の提供品質の向上も期待され、成長につながるだろう。 (2) 半導体市場の動向 パワー半導体は現在、電動車のほか、太陽光発電のような再生可能エネルギー分野や産業機械、鉄道・電車、情報通信機器等に使用されているが、電子機器の小型化や高性能化が進む中で、さらなる半導体の高性能化や小型化が求められている。現在主流のSi(シリコン)パワー半導体では、素材自体の限界から大幅な性能改善は難しいとされており、対策としてSiC(炭化ケイ素)やGaN(窒化ガリウム)といった素材を用いた次世代パワー半導体が注目されている。経済産業省の「半導体・デジタル産業戦略」(2023年6月)においてもこれらの素材を用いた次世代パワー半導体の市場規模拡大を予想しており、SiCパワー半導体については2021年の約1,400億円から2030年には約3.4兆円と、約24倍に拡大するとしている。市場拡大に比例して信頼性試験需要の増加も十分期待される。 次世代パワー半導体とともに同社が注目しているのが、先端半導体パッケージである。先端半導体パッケージとは、1つのパッケージに異なる機能を持つ複数の半導体を高密度に集積することにより、高性能や小型化、低消費電力を実現する技術である。前掲の「半導体・デジタル産業戦略」では、先端パッケージ戦略を3段階に分けて策定しており、ステップ1として、素材・装置メーカーが集約する先端パッケージ開発拠点を設立し、国内に点在するコンソーシアム(共同事業体)を束ねて、先端集積・実装技術を創出するとともに、次世代の装置や素材を開発し、半導体に係るデバイスメーカーやファウンドリ等に提案する。ステップ2において2020年代後半以降に求められている2.5D/3Dパッケージング技術やシリコンブリッジ、ハイブリッドボンディングなどを開発し、2nm世代以降で必須となるチップレット技術を確立し、ステップ3では光チップレット、デジタルチップとアナログチップを混載するアナデジ混載SoC技術を確立する。パッケージング技術としては、現状は2.5D実装が一般的であるが、今後はシリコンブリッジや3D実装が進むことが予想され、同社はステップ2の段階で、同社の強みとする半導体基板への環境試験や分析・故障試験、素材の切断や断面研磨加工の知見が生かせる、先端半導体パッケージの信頼性試験の需要が拡大すると見ており、設備導入や人材増強等の体制作りを進めている。 (執筆:フィスコアナリスト 村瀬 智一) 《HN》 記事一覧 |