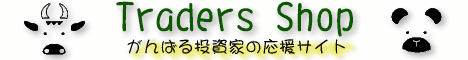
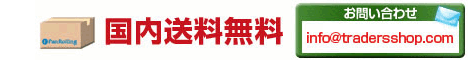
| 携帯版 |
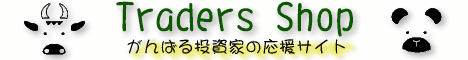
|
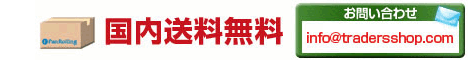
|
|
フィスコ投資ニュース配信日時: 2025/04/03 16:51, 提供元: フィスコ 一正蒲 Research Memo(5):2025年6月期中間期は主力製品の販売数量増で増収、2ケタ増益(1)*16:51JST 一正蒲 Research Memo(5):2025年6月期中間期は主力製品の販売数量増で増収、2ケタ増益(1)■一正蒲鉾<2904>の業績動向 1. 2025年6月期中間期の業績概要 2025年6月期中間期の連結業績は、売上高19,053百万円(前年同期比1.1%増)、営業利益1,023百万円(同10.7%増)、経常利益1,090百万円(同16.3%増)、親会社株主に帰属する中間純利益953百万円(同36.0%増)と、増収増益となった。特に中間純利益の伸び率が大きくなったが、これはインドネシアの合弁会社KIFへの出資比率を40%から75%に引き上げ連結子会社化したことに伴い、株式の段階取得に係る差益(過去出資分の時価評価による差益)126百万円を特別利益に計上したことによる。また、期初計画に対しても、売上高で95.3%、営業利益で93.0%の達成率となり、ほぼ計画どおりの進捗と言えるだろう。水産練製品・惣菜事業は、スティックタイプのカニかまを中心とした主力商品の販売数量が伸長したほか、おせち商品も過去最高の売上高を達成するなど、売上高は前年同期を1.8%上回り全体の売上高の伸びをけん引した。一方、きのこ事業は、販売価格は前年を上回ったものの、需要の高まる秋口以降も平年より気温が高い日が続くなど販売数量が減少し、売上高は前年同期を4.0%下回った。損益面では、主原料のすり身価格など原材料価格の上昇が一服し、販売数量の増加による工場の稼働率向上、合理化投資による省人化などにより売上総利益率は22.1%と前年同期を1.6ポイント上回った。売上総利益は同9.0%増と前年同期を349百万円上回った。販管費は、販売数量増による物流費増、カニかま発売50周年キャンペーンなど販促費増により、同8.5%増加し前年同期を250百万円上回ったが、売上総利益の増加により吸収し営業利益は同2ケタの増益となった。 営業利益の増減分析では、カニかまの拡販による販売数量の伸長による増収効果で2.0億円、北米産冷凍すり身など原材料価格の上昇が一服したことによる原価コストダウンで1.1億円、合理化投資による省人化、歩留まり改善などの生産性向上によるコストダウンで1.8億円の計4.9億円の利益拡大となった。一方、電力・燃料価格の上昇によるエネルギーコストアップで0.9億円、設備投資による減価償却費増加やその他経費の増加により0.5億円、販売数量の増加に伴う物流費増加、販促強化に伴う販促費の増加による販管費の増加で2.5億円の計3.9億円の減益要因となり、営業損益は1.0億円の増益となった。 2. 事業セグメント別動向 (1) 水産練製品・惣菜事業 売上高は16,920百万円(前年同期比1.8%増)、セグメント利益は1,020百万円(同28.7%増)と増収、2ケタ増益となった。カニかま50周年記念販促施策などにより「サラダスティック」の販売数量が伸長したことが収支ともに大きく貢献した。カニかまは、1974年9月に初代カニかま「かに太郎」を発売してから50周年を迎えた。各チェーンストアの売場コンテストの実施、売場取扱いの拡大を図るほか、消費者へのプレゼントキャンペーンなどを展開した。コスパ(コストパフォーマンスの略)、タイパ(タイムパフォーマンスの略)、健康などを志向する共働き・単身、高齢者世帯などの消費者ニーズとカニかまの商品性がマッチし、売行きは着実に右肩上がりとなっているようだ。加えて、冷凍保存を可能にし、保存性・利便性を高めたお徳用商品である「小判てんぷら」も消費者ニーズを的確に捉えて売上が伸長した。また、おせち商戦でも、得意先と店頭展開時期を早期化する「早出し」への取り組みが奏功し、同社としては過去最高の売上高となった。同社調べによれば市場全体としては売上高、数量とも前年を割り込む中で、同社はシェアを上昇させた形だ。主原料から副材料まで国産原料を100%使用し、素材本来の味を引き出した「国産原料100%『純』シリーズ」の売り場作りコンテストによる周知施策など、差別化商品の拡販強化も奏功したようだ。特に、2024年3月に開催された第75回全国蒲鉾品評会(日本かまぼこ協会主催)において、最優秀賞にあたる農林水産大臣賞を受賞した「国産甘鯛入り御蒲鉾 京禄(けいろく)」の売上高が前年の6倍、数量が同7倍と伸長し、おせち商品の売上増加に貢献した。 損益面では、販売数量伸長による工場稼働率の向上、自動化・省人化によるコストダウンに加えて、主原料である北米産すり身において、価格が急騰した2023年Aシーズン(1〜6月)に比べて2024年Aシーズンは価格が落ち着いたため、原価を押し下げた。これによりエネルギーコストの上昇や物流費、販促費の増加をカバーし、セグメント利益率は6.0%と前年同期を1.3ポイント上回り、セグメント利益は同28.7%増となった。 (2) きのこ事業 売上高は1,945百万円(前年同期比4.0%減)、セグメント損失は88百万円(前年同期は57百万円の利益)と、減収減益となった。野菜、きのこの市況は好調に推移し、まいたけの価格も上昇し前年同期を上回った。しかし、きのこの需要が高まる2024年の秋口以降も平年より気温が高い日が続き、販売数量が減少した。また、夏場の高温と残暑の影響から例年どおりの工場の空調管理では思うような生育を確保できず、秋口に一株重量が低下したことも、販促機会を逃すロスにつながった。損益面では、合理化・省人化投資により生産性向上を進めているが、エネルギー価格や培地など原料価格の上昇によるコストを吸収できず減益となった。 (3) その他 売上高は186百万円(前年同期比11.0%減)、セグメント利益は88百万円(同16.9%増)と、減収増益となった。運送事業は、主に定期輸送便の一部終了、設備投資関連費用の増加により減収減益となった。倉庫事業は、前年同期を上回る入庫量を獲得したことで荷役料収入を伸ばしたものの、在庫水準は低調に推移し減収となったが、収益性改善に向けた庫内管理の最適化を進めた結果増益となり、全体では減収増益となった。 (執筆:フィスコ客員アナリスト 松本章弘) 《HN》 記事一覧 |