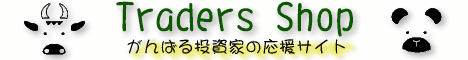
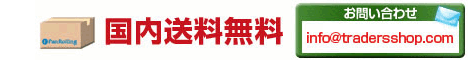
| 携帯版 |
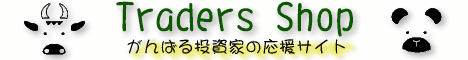
|
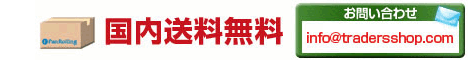
|
|
フィスコ投資ニュース配信日時: 2025/04/23 12:09, 提供元: フィスコ SOLIZE Research Memo(9):従来領域と新規領域の掛け合わせにより成長を加速(2)*12:09JST SOLIZE Research Memo(9):従来領域と新規領域の掛け合わせにより成長を加速(2)■SOLIZE<5871>の中長期の成長戦略 (2) コンサルティング・エンジニアリング事業領域 ものづくり変革で培ったコア技術により、企業課題・社会課題の解決を行うコンサルティング及びエンジニアリングサービスの提供を行う。 成長戦略としては、自動車新領域への展開等、既存コンサルティング事業の成長拡大、SaaS事業による非労働集約型ビジネスの拡大を推進する。具体的には、第1にコンサルティング事業の拡大のために、AI技術及びデジタルテクノロジー活用によるコンサルティング事業の付加価値向上、自動車新領域への対象領域拡大、採用力強化と若手人財の早期育成を図る。第2に、SpectA事業(SaaSビジネス)の拡大のために、コンサルティング事業と同領域での提案や事業拡大、ビジネス拡大に向けた営業体制の強化を計画する。第3に、MBDやサイバーセキュリティ等の高付加価値領域の拡大を目指して、自動車の制御開発を中心として自動車開発へのAI・クラウド活用や数理モデルの提供、ECU開発等のソフトウェア開発におけるサイバーセキュリティ対応支援を強化する。 現在、自動車の新領域は大きな変革期で、特にDXの加速に関して多くの引き合いがあることから、採用強化のうえ同社グループの持つ変革力で成長を図る。また、同社グループが独自で開発したAIプロダクトを、コンサルティング事業との連携により次の事業拡大の柱とすることを考えている。さらに技術領域で一番付加価値の高い自動車制御のモデルベース開発や、サイバーセキュリティ対応支援などにより拡大を図る。 (3) ビジネスインキュベーション事業領域 新たな事業領域であり、社会・産業課題の解決に向けた新規事業の開発及び運営を行う。 成長戦略としては、デジタルテクノロジーを活用してビジネスインキュベーションを通じた社会変革を実現することで、経済的価値と社会的価値の創出を同時に実現する。具体的には、第1に新規領域での事業開発の推進のために、採用ブランディング強化による意欲ある事業オーナーの採用、事業立ち上げや新規事業会社の運営サポート体制等の強化、起業経験者の採用や活用を推進する。第2に、CVC(社外のベンチャーに対して行う投資活動)等による外部パートナーとの連携のために、成長性のある市場及びその市場ニーズや事業シーズの両面で広く可能性を探索、アントレプレナー、VC、事業会社、CVC、自治体などの支援者を中心に人的ネットワークを開拓、グローバルのコンソーシアムやコミュニティへの積極参加によりネットワークを開拓する。 2025年1月には、ソフトウェア事業を承継する(株)STELAQを分社化した。ソフトウェア事業を展開していたソフトウェアエンジニリング部は、3年で200名を超える規模の組織に成長した。こうしたスタートアップ的な事業を多く作ることが、ビジネスインキュベーションの非常に大事な事業内容となるため、今後は中核事業会社としてCVC等を含めた外部とのパートナー連携を進める計画である。 (4) 投資戦略 持株会社が担うグループ戦略であり、健全な財務状況を背景としたM&A・スタートアップ投資の積極活用によりインオーガニック成長を実現するとともに、既存ビジネス成長に貢献する新領域・新技術の獲得の両立を目指して事業成長を加速する。具体的には、M&A活用による拡張の加速としては、既存領域(国内・自動車)及び既存技術(機械系)から、新領域(ヘルスケア・宇宙・エネルギー、北米・アジアなど)、新技術(ソフトウェア・AI・ロボティクス・超電導など)、新領域と新技術の組み合わせなどを計画する。同社グループは創業以来、常に先端技術を日本に取り込んで成長を遂げてきたことから、新領域での連携を深める投資を重視している。 また、日本・北米・アジアにおいて、スタートアップ(急成長する企業)への投資を計画している。同社グループの高度な技術・開発力による独自のスタートアップ・エコシステム(スタートアップのために企業や組織が相互に関係し合って協力する仕組み)の構築を目指す。同社はスタートアップに出資や技術支援をすることで、技術獲得、人材育成、インカムゲイン、キャピタルゲインを、また同社がファンドを通じて出資する場合には、ファンドからの情報収集やキャピタルゲインを狙う。既に、ファンドにより米スタートアップに協調投資を行い、機構系設計・開発の支援を行っている。同社グループとしては、CVC投資で単純にキャピタルゲインを得るだけではなく、人と技術の供給を行うことでスタートアップの成長の加速を推進する考えだ。 (5) 人財戦略 持株会社が行うグループ戦略であり、経営戦略と連動した人的資本経営の実践を目指す。具体的には、既存事業価値を最大化するための人財マネジメントの仕組み構築、掛け合わせと新規領域での能力拡張を加速する高付加価値人財・価値創造人財を確保する。また、経営戦略を実現するための人事基盤の構築のために、採用投資、人事制度投資、人財育成・組織開発投資、社員満足度・エンゲージメント投資を計画している。継続投資を行っている人財戦略では、経営戦略と連動した採用、人財育成、あるいはエンゲージメントが重要となる。同社が持株会社化することで、各事業の成長は遠心力で加速するが、一方でグループとしての求心力が必要となる。人財戦略の実践によってグループマインドなどの求心力を強化し事業を拡大する。 採用強化では、2022年12月期から経験者採用を強化し、多くのハイエンド人財を確保しており、2024年12月期は約300名を採用している。2027年12月期には500名の採用を目指す。 以上のように、同社グループは持株会社体制に移行し、持株会社がグループ戦略を推進し、3つの中核事業会社が事業戦略を推進することで2027年12月期に売上高400億円を達成し、長期的には2033年12月期に1,000億円への拡大を展望している。そのために投資が先行するものの、事業拡大に伴い利益率も徐々に改善すると、弊社では考える。 同社グループは、成長戦略の推進とともに、サステナビリティへの取り組みも推進している。「環境」への取り組みでは、脱炭素社会の実現に貢献すべく、同社グループの事業活動による温室効果ガス排出量(Scope1及びScope2)を、2030年度までにカーボンニュートラルとする目標を定め、社用車へのZEV(電気自動車や燃料電池車などのゼロエミッション車)の導入、事業所の電力を再生可能エネルギーや実質再エネへの転換等に取り組んでいる。「社会」への取り組みとしては、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が推進する「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」において、慶應義塾大学が代表機関を務める「デジタル駆動 超資源循環参加型社会 共創拠点」に参画している。近年、企業の環境、社会、企業統治への取り組みに基づいて投資銘柄を選択するESG投資が、日本市場や欧州市場を中心に急拡大している。その意味からも、同社グループの取り組みが注目される。 (執筆:フィスコ客員アナリスト 国重 希) 《HN》 記事一覧 |